こんにちは!りらくです。
多くの保険商品がありますが、何に入ればいいのか分からなくなることも多いと思います。
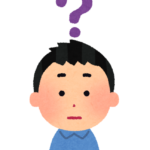
公的保険と民間保険ってどう違うの?

掛け捨てとか貯蓄型って何?どっちがお得なの?
保険は「万が一」に備える大切な制度ですが、種類が多くてわかりにくいのが正直なところ。何となく加入してしまい、よく理解できていない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、公的保険・民間保険・共済の違いや、掛け捨て型と貯蓄型の特徴、さらには保険料控除のしくみまで、初心者にもわかりやすく解説します。これを読めば、あなたにとって本当に必要な保険が見えてくるはずです。
今回の記事では、以下の本の内容も踏まえて解説しております。
目次
公的保険とは?「国が用意する最低限の保障」
まず理解しておきたいのが「公的保険」です。これは、国や自治体が運営する保険制度で、国民全員が加入対象です。生活する上で起こりうるリスクに対し、最低限の保障をしてくれる仕組みです。
公的保険の主な種類
| 保険の種類 | 内容 |
| 健康保険 | 病気やけがの治療費の自己負担を軽減(原則3割負担) |
| 国民年金・厚生年金 | 老後・障害・死亡に備えた年金制度 |
| 雇用保険 | 失業時や育児・介護休業時の所得補償 |
| 労災保険 | 業務中の事故や病気に対する保障 |
| 介護保険 | 高齢期に必要な介護サービスの費用を補助 |
これらの保険は、会社員であれば給与から自動的に天引きされ、個人事業主の場合は国民健康保険や国民年金に自分で加入します。
ポイント:
- 公的保険は「生活の土台を支える保障」
- 加入は義務。保険料は収入に応じて負担

公的保険で必要最低限は保障されているんだね
民間保険とは?「自分のニーズに合わせて選べる補償」
公的保険だけではカバーしきれない部分を補うのが「民間保険」です。保険会社が提供している任意加入の保険で、目的やライフスタイルに応じて選べます。
民間保険の代表的な種類
- 医療保険:入院・手術費などに備える
- がん保険:がんに特化した補償内容
- 生命保険:死亡時に家族へ保険金が支払われる
- 学資保険:子どもの教育資金を積み立てる
- 個人年金保険:老後の生活資金を準備
民間保険のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| 自分に必要な保障を選べる | 保険料がかかる(特に長期契約) |
| 公的保険でカバーしきれない部分を補える | 商品の種類が多く選びにくい |
| 保険料控除の対象になることもある | 長期契約で途中解約すると損することも |

必要以上に民間保険に入ると家計が苦しくなるから、本当に必要なものだけに加入するようにしないといけないね
共済とは?「割安で安心な非営利の助け合い保険」
「共済」とは、農協(JA)、生協、労働組合などが提供する、非営利の相互扶助制度です。民間保険と似ていますが、運営母体が違うため、コスト面や仕組みに特徴があります。
共済の特徴
- 非営利:利益を追求しない分、保険料が割安
- 加入対象に制限あり:生協の組合員、JAの組合員など
- 保障はシンプル:選択肢は少ないが基本的な補償はある
共済と民間保険の違い
| 項目 | 民間保険 | 共済 |
| 運営主体 | 保険会社(営利) | 組合や団体(非営利) |
| 加入対象 | 誰でも可能 | 組合員や関係者に限られる |
| 保険料 | 割高になりやすい | 比較的安価 |
| 補償内容 | 商品が豊富でカスタマイズ可能 | シンプルで選択肢は少ない |
| 保険金の支払い | 一定の審査あり | 比較的スムーズ |
ポイント:共済は費用を抑えて最低限の保障を得たい人におすすめです。

コストが低い分、保障範囲は狭いんだね
掛け捨て型 vs 貯蓄型:どちらの保険を選ぶべき?
民間保険や共済には「掛け捨て型」と「貯蓄型」の2種類があります。自分に合ったタイプを選ぶことが、賢い保険選びの第一歩です。
掛け捨て型保険とは?
- 保険料は安い
- 保険期間が終わってもお金は戻らない
- 「保障だけが欲しい」という人向け
「保険に入るなら、保険機能に特化した掛け捨てがいい」とよく言われます。
—— 小林 義崇『すみません、金利ってなんですか?』
「お金を増やしたい」という場合は、純粋に仕事に励むか、貯蓄や投資をがんばればいい。
一方、「お金は最低限でいい、無理して増やそうと思わない」という人で、万が一の保障を考えている場合は、掛け捨て型の保険を選ぶべきです。
貯蓄型保険とは?
- 保険料は高め
- 満期や解約時に返戻金がある(資産形成になる)
- 長期的に保険+お金を準備したい人向け
比較表:掛け捨て型 vs 貯蓄型
| 項目 | 掛け捨て型 | 貯蓄型 |
| 保険料 | 安い | 高い |
| 解約返戻金 | なし | あり |
| 契約期間 | 定期が多い | 終身・長期が多い |
| 資産形成 | 不可 | 可能 |
| 柔軟性 | 高い | 低い |

将来のことは分からないけど、基本的に「掛け捨て型」で月々の支払いも必要最小限にする方が良いかもね
保険料控除とは?保険に入ると税金が安くなる!
保険に加入していると、確定申告や年末調整で「保険料控除」が受けられます。これは、支払った保険料の一部を所得控除として差し引いてもらえる制度で、結果的に税金が安くなります。
主な保険料控除の種類
| 控除の種類 | 対象保険 | 最大控除額(所得税) |
| 生命保険料控除 | 死亡・医療・がん保険など | 年間最大12万円(新制度) |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険・がん保険など | 年間最大4万円 |
| 個人年金保険料控除 | 年金積立型の生命保険 | 年間最大4万円 |
| 地震保険料控除 | 地震・火災保険(特約含む) | 年間最大5万円 |
※ 共済の保険(生命共済など)も控除対象になることがあります。
控除を受けるには?
- 年末調整や確定申告時に「控除証明書」の提出が必要
- 1年の途中で保険に加入した場合も対象になる
年末調整や確定申告時の控除については、以下記事でも紹介しています。

使える節税制度はしっかり押さえておかないとね!
まとめ:保険は“目的”で選ぶのがコツ!
保険にはさまざまな種類があり、何に入ればいいか迷ってしまいがちです。でも、大切なのは「何のために保険に入るのか」を自分で明確にすることです。
- 「最低限の保障があればいい」→ 掛け捨て型保険+共済
- 「老後に備えたい」→ 貯蓄型保険や個人年金保険
- 「家族に何かあったときの安心がほしい」→ 生命保険や医療保険
- 「保険料を抑えつつ補償を得たい」→ 共済を検討
さらに、保険料控除も活用すれば、実質的な負担を減らすことも可能です。
保険は“備え”であり、“投資”ではありません。無理にお金を増やそうとせず、自分の生活に合った堅実な選択を心がけましょう。
以下の動画でも、必要な保険に関する考え方が紹介されているので、参考にしてみてください。
出典:両学長 リベラルアーツ大学
動画中で紹介された書籍はこちらです。

将来のためにも、保険について考えてみよう!
それでは、今回の内容は以上となります!
今回も読んでいただき、ありがとうございました!!
もしこの記事が良かったら、SNSでの共有および以下をクリックしていただけると大変喜びます!
にほんブログ村
にほんブログ村




コメント