こんにちは!りらくです。
今回は年金やiDeCoについてです。

年金って言葉はよく耳にするけど、実際の仕組みはよくわからない…
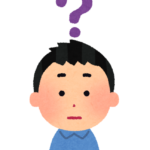
iDeCo(イデコ)って最近よく聞くけど、どんな制度なの?
こんな疑問を抱いている方、多いのではないでしょうか?
年金制度は難しそうに見えますが、基本の仕組みを理解すれば意外とシンプルなんです。
日本の年金制度は、1階部分の国民年金(基礎年金)と2階部分の厚生年金の2階建て構造が基本となっています。そして、それだけでは将来の生活費が足りないかもしれない…という人のために、自分で積み立てて運用する「iDeCo(確定拠出年金)」という3階部分が用意されています。
今回の記事では、この「2階建て+iDeCo」の年金構造を、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。これを読めば、あなたも年金制度の基礎がバッチリ理解できるはず!
さあ、早速始めていきましょう!
今回も以下の本の内容を踏まえて、紹介しております。
目次
日本の年金制度の全体像
1階部分:国民年金(基礎年金)とは?
国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳までの全ての国民が加入する年金です。会社員でも専業主婦でも学生でも、基本的に全員が対象です。
この国民年金は、「老齢基礎年金」として、老後の最低限の生活費を保障する役割を担っています。
- 受給開始年齢:原則65歳(60歳〜70歳の間で受給時期を選べる)
- 受給額:2025年度基準で満額年間約78万円(月額約65,000円)
- 保険料:毎月の固定額(2025年度の保険料は16,990円)
また、繰り上げ受給や繰り下げ受給の制度もあります。例えば、60歳から受け取りを開始する場合、受給額が毎月0.5%ずつ減額されます。一方、70歳まで繰り下げると、毎月0.7%ずつ増額されるため、受給額を大きく増やすことができます。
2階部分:厚生年金 — 会社員や公務員が加入する年金制度
厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金制度です。国民年金が老後の最低限の生活費をカバーするのに対して、厚生年金は現役時代の収入を補填するための制度です。
- 加入対象者:会社員、公務員(アルバイトやパートも条件を満たせば加入)
- 受給開始年齢:原則65歳
- 受給額:給与や加入期間に応じて決定される
- 計算方法:報酬月額 × 加入期間 × 支給率
例えば、現役時代の収入が高いほど厚生年金の受給額も多くなります。また、長期間加入しているほど受給額が増加します。
さらに、厚生年金には「遺族厚生年金」や「障害厚生年金」の制度もあり、配偶者や子ども、障害者の生活をサポートする役割も果たしています。

国民全員が対象の「国民年金」と会社員などが対象の「厚生年金」の2階構造なんだね
iDeCo(イデコ) — 自分で作る3階建ての年金
iDeCo(イデコ)とは、「個人型確定拠出年金」のことで、自分で掛金を拠出し、その資金を運用して将来の年金資金を準備する制度です。国が提供する老後資金の積立制度で、税制優遇を受けながら資産形成ができるのが特徴です。
iDeCoの仕組み
- 掛金の拠出:
- 毎月一定額を拠出(1,000円単位で設定可能)。
- 自営業者や会社員、公務員など職業ごとに掛金の上限額が異なる。
- 運用商品を選択:
- 投資信託、定期預金、保険商品などから自由に選択可能。
- 自分のリスク許容度や運用期間に応じて商品を選ぶ。
- 運用益の再投資:
- 運用期間中の運用益は非課税で再投資される。
- 受取時期:
- 原則60歳以降に受け取る(加入期間によって受取開始年齢が異なる)。
- 受取方法は一時金(一括)または年金形式で選択可能。
iDeCoの加入対象者と掛金の上限額
| 加入区分 | 月額掛金の上限 |
| 自営業者 | 68,000円 |
| 会社員(企業型DCなし) | 23,000円 |
| 会社員(企業型DCあり) | 20,000円 |
| 公務員 | 12,000円 |
| 専業主婦(夫) | 23,000円 |
iDeCoの税制優遇
iDeCoには3つの税制優遇があります:
- 拠出時の所得控除:
- 掛金全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される。
- 運用期間中の非課税:
- 運用益は非課税で再投資されるため、効率的に資産を増やせる。
- 受取時の税制優遇:
- 一時金で受け取る場合:「退職所得控除」が適用される。
- 年金で受け取る場合:「公的年金等控除」が適用される。
iDeCoは掛金が所得控除の対象になることから、年末調整や確定申告などにも関わってきます。こちらについて紹介した記事は以下になります。
iDeCoのメリット
- 節税効果が大きい: 掛金全額が所得控除されるため、節税しながら資産形成ができる。
- 運用益が非課税: 長期間の非課税運用で資産が増えやすい。
- 老後資金の確保: 自分のライフスタイルやリスク許容度に応じた運用が可能。
- 資産運用の経験が積める: 投資信託などで運用経験が得られる。
iDeCoのデメリット
- 途中引き出しができない: 原則60歳まで引き出しが不可。
- 手数料がかかる: 加入時、運用時、受取時に手数料が発生する。
- 運用リスクがある: 投資信託などの場合、元本割れのリスクがある。
- 加入期間に制約がある: 60歳までの加入期間が短いと受取開始年齢が遅くなる。
iDeCoの受取方法
- 一時金として一括受取:退職所得控除が適用され、控除額が大きい。
- 年金として分割受取:公的年金等控除が適用され、毎年の税負担を抑えられる。
- 併用受取:一部を一時金、残りを年金として受け取ることも可能。
一括受取に適用できる退職所得控除については、1度使うと10年経過しない使用できないようにルールが変更となりました。そのため、60歳時点でiDeCoで運用した資金を受け取る際に退職所得控除を使用すると、65歳で定年退職した際に受け取る退職金には控除が適用できないため、注意が必要です。
出典:両学長 リベラルアーツ大学
企業型DC — 企業が運営する確定拠出年金制度
iDeCoと似たようなもので企業型DCという制度もあります。こちらは、企業が従業員のために掛金を拠出し、その掛金を運用していく年金制度です。
企業型DCの掛金は企業が設定するため、個人で積み立てるiDeCoとは異なります。
仕組みと特徴
- 掛金の拠出:
- 企業が毎月、一定の掛金を従業員の年金口座に拠出します。
- 従業員自身が追加で掛金を拠出することができる「マッチング拠出」も可能です。
- 運用の選択:
- 従業員自身が運用商品(投資信託、定期預金、保険商品など)を選択し、その結果によって年金資産が増減します。
- 運用益の非課税:
- 運用期間中の運用益は非課税で再投資されるため、資産形成が効率的です。
- 受取時の税制優遇:
- 退職金として一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用され、節税効果があります。
企業型DCのメリット
- 税制優遇: 掛金拠出時・運用期間中・受取時に税制優遇がある。
- 資産形成: 長期的な資産運用が可能。
- 老後資金の確保: 公的年金の不足分を補える。
企業型DCのデメリット
- 運用リスク: 運用結果によって受取額が変動する。
- 引き出し制限: 原則60歳まで引き出せない。
- 運用商品の選択責任: 自分で運用商品を選ぶため、リスク管理が必要。
iDeCo vs 企業型DC — 違いと選び方
| 項目 | iDeCo | 企業型DC |
| 加入者 | 自営業、会社員、公務員 | 企業に勤務している従業員 |
| 掛金の負担 | 自己負担 | 企業が負担(従業員負担も可) |
| 掛金上限 | 68,000円(自営業) 20,000円(公務員) | 55,000円 |
| 税制優遇 | 掛金全額が所得控除 | 企業負担分も非課税 |
| 受給開始年齢 | 60歳〜 | 60歳〜 |
| 運用責任 | 自己責任 | 自己責任 |

こうやって比較すると、似ているところもあれば、違うところも明確になるね!
まとめ:年金制度の基本を押さえて、老後の備えを万全に!
日本の年金制度は、1階部分の国民年金で最低限の生活費をカバーし、2階部分の厚生年金で現役時代の収入を補う仕組みです。
しかし、それだけでは将来の生活資金が足りないかもしれない…という人のために、「iDeCo(確定拠出年金)」という3階部分が登場しました。
特に、2024年12月の改正で掛金上限額が引き上げられたことにより、公務員やDB加入の会社員でも月額20,000円まで掛金を増やせるようになり、より多くの資金を積み立てられるようになりました。
年金制度の基本をしっかり押さえて、早めの準備で将来の安心感を手に入れましょう!
老後の不安を減らし、充実した生活を送るために、今からできることを始めてみませんか?

年金制度も上手く活用して、将来に備えよう!
それでは、今回の内容は以上となります!
今回も読んでいただき、ありがとうございました!!
もしこの記事が良かったら、SNSでの共有および以下をクリックしていただけると大変喜びます!
にほんブログ村
にほんブログ村




コメント