にほんブログ村
こんにちは、りらくです!
株式投資を始めると、株価の値動き(キャピタルゲイン)だけでなく、配当金(インカムゲイン)がもらえる瞬間は嬉しいものですよね。
でも初めて配当金を受け取ったとき、こんな疑問が出てきませんか?

あれ?配当金からけっこう税金が引かれてる…
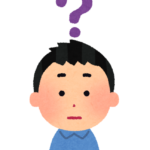
配当控除って聞いたことあるけど、どうやって使うの?

自分は使ったほうがいいの?それとも損?
実は、配当金の税金は確定申告をすることで減らせる可能性があります。それが配当控除です。
今回は、初心者でもスッキリ理解できるように、仕組みから使い方、使えないケース、注意点、年収別の有利不利シミュレーションまで詳細に解説します。
目次
配当金と税金の仕組み
配当控除を理解するための第一歩は、配当金にかかる税金がどう計算されているかを正しく知ることです。
(1)配当金の課税構造
上場株式の配当金には、以下の税金がかかります。
- 所得税:15.315%(復興特別所得税を含む)
- 住民税:5%
つまり、合計 20.315% が差し引かれます。
例:配当金が10,000円の場合
- 所得税:1,531円
- 住民税:500円
- 手取り:7,969円
特定口座(源泉徴収あり)で運用している株の配当金は証券会社が税額を源泉徴収し、差し引かれた後の金額が口座に入金されます。
(2)特定口座(源泉徴収あり)の場合
多くの初心者が利用する特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が自動で納税まで行ってくれます。
そのため、原則として確定申告は不要です。
しかし――確定申告をすると一部税金が戻る可能性があります。それが次章で解説する配当控除です。

約20%も税金で取られているから、配当控除をやってみる価値はありそうだね!
配当控除とは?
(1)配当控除が生まれた背景
配当控除は、二重課税を調整する制度です。
なぜ二重課税になるかというと…
- 企業が利益から法人税を支払う
- 残った利益を株主に配当する
- 株主は配当に対して再度、所得税・住民税を支払う
→ 同じ利益に法人税+個人の税金が二重にかかっている状態になります。
この不公平を軽減するため、総合課税で申告すると一定額の税額控除が受けられるのが配当控除です。
(2)配当控除の仕組みと控除率
上場株式の場合、総合課税で申告すると次の控除が受けられます。
- 所得税控除率:配当所得 × 10%
例:配当金10万円の場合
- 所得税控除:10万円 × 10% = 1万

この例の場合だと、何もしなければ約2万円が税金として取られてしまうから、配当控除はお得だね!
配当控除が使えない(または使わないほうがいい)ケース
配当控除は万能な節税策ではありません。制度的に適用されないケースや、使うと損になるケースがあります。
(1)外国株式の配当
- 米国株などの外国株式配当には配当控除は適用されません。
- 外国株は外国税額控除の対象となります。
配当控除が使えるのは「上場株式の配当」、「公募株式投資信託の分配金」となります。
(2)NISA口座で受け取った配当
- NISAは非課税口座なので、配当控除を使う必要がありません。
- 確定申告をしても還付はありません。
(3)申告分離課税を選んだ場合
- 配当金を申告分離課税で申告すると、配当控除は適用されません。
- 総合課税を選択する必要があります。
(4)キャピタルゲイン(売却益)
- キャピタルゲインには配当控除は使えません。
- 株式売却益は譲渡所得に分類され、原則として申告分離課税(20.315%)で課税されます。
- 売却損がある場合は損益通算・繰越控除が節税の手段となりますが、配当控除とは別制度です。
(5)高所得者の場合
- 課税所得が33%以上の税率帯にある人は、総合課税を選ぶと税率が高くなり、配当控除を使っても逆に増税になることがあります。
- 所得が900万円を超える方は33%以上の税率帯になるため、申告不要制度を選んだほうが有利です。
(6)少額配当の場合
- 配当が少なく、配当控除による還付額が数百円程度しかない場合は、申告の手間に見合わないこともあります。

配当控除には制限もあることを認識しておこう!
年収別 有利/不利シミュレーション
配当控除は、年収・課税所得・配当額によって有利か不利かが変わります。
ここでは、分かりやすく年収別にどちらの課税方式が有利かを整理します。
(1)前提条件
- 配当金:10万円(上場株式)
- 年収は給与所得のみ
- 控除は基礎控除のみで計算
(2)年収別比較表
| 年収 | 税率(総合課税) | 総合課税+配当控除 | 申告不要 |
| 300万円 | 5% | 還付あり(有利) | ほぼ同等 |
| 500万円 | 20% | 還付あり(有利) | 少し損 |
| 900万円 | 23% | 還付小(トントン) | トントン |
| 1,200万円 | 33% | 増税(不利) | 有利 |
(3)ポイント整理
- 年収900万円以下:総合課税+配当控除が有利になるケースが多い
- 年収900万〜1,000万円前後:トントンになりやすい
- 年収1,000万円超:申告不要制度のほうが有利な場合が多い

年収900万円までならお得になることが多いと覚えておこう!
配当控除を使う申告の流れ
配当控除を利用するには、確定申告(総合課税の選択)が必須です。
初心者向けに、具体的な手順を整理します。
(1)必要な書類
- 証券会社の年間取引報告書(配当額と税額が記載)
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- (e-Tax利用時)ICカードリーダーやスマホ環境
(2)申告の流れ
- 年間取引報告書を確認
- 配当額と源泉徴収税額をチェック
- 課税方式を「総合課税」に設定
- 申告書作成画面で「配当所得 → 総合課税」を選択
- 配当控除の金額を入力
- 所得税:配当所得×10%
- 住民税は「申告不要」にチェック
- 申告書を提出
- e-Taxまたは書面提出(e-Tax推奨)
💡 実務のコツ
- 複数の証券口座がある場合は、すべての口座の年間取引報告書が必要です。
- e-Taxを使えば自動計算されるため、初心者でも入力ミスを防げます。

年間取引報告書の入手方法は事前に確認しておかないとね
住民税申告の注意点
配当控除を適用する場合、住民税の申告方法にも注意が必要です。
(1)会社に配当収入を知られたくない場合
総合課税を選ぶと、住民税の課税所得にも配当が反映されます。
勤務先は住民税の金額から副業や配当を推測できる場合があるため、知られたくない場合は以下の方法を使います。
- 住民税申告で普通徴収を選ぶ
- 所得税では総合課税、住民税では申告不要制度を選ぶ(自治体によって可否あり)
※普通徴収の場合には住民税も総合課税として処理されますので、課税所得が1000万以下の方は約7.2〜7.5%の住民税率が発生します。
(2)住民税での配当控除
住民税でも配当控除が受けられますが、所得税とは別計算です。
自治体によって取り扱いが微妙に違うこともあるため、確認が必要です。

特に勤務先に知られても問題なかったり、副業などがない場合には「申告不要」にすると住民税が最も安くなるよ!
まとめ
- 配当控除は、総合課税で申告することで二重課税を調整し税金を減らせる制度
- 外国株・NISA・分離課税では使えない
- 高所得層は総合課税で増税になる可能性があるため、年収・配当額ごとに有利な方式を選ぶ
- 住民税の申告方法を工夫すれば、勤務先に知られず節税が可能
初心者はまず、
- 自分の年収・配当額・課税方式を整理
- 国税庁のシミュレーションで総合課税が有利か確認
- 配当控除を適用するなら、住民税の扱いもセットで検討
これだけで、無駄な税金を払わずにすみます。

配当金を多く手に入れたい人は、この制度の利用を検討しましょう!
それでは、今回の内容は以上となります!
今回も読んでいただき、ありがとうございました!!
もしこの記事が良かったら、SNSでの共有および以下をクリックしていただけると大変喜びます!
にほんブログ村
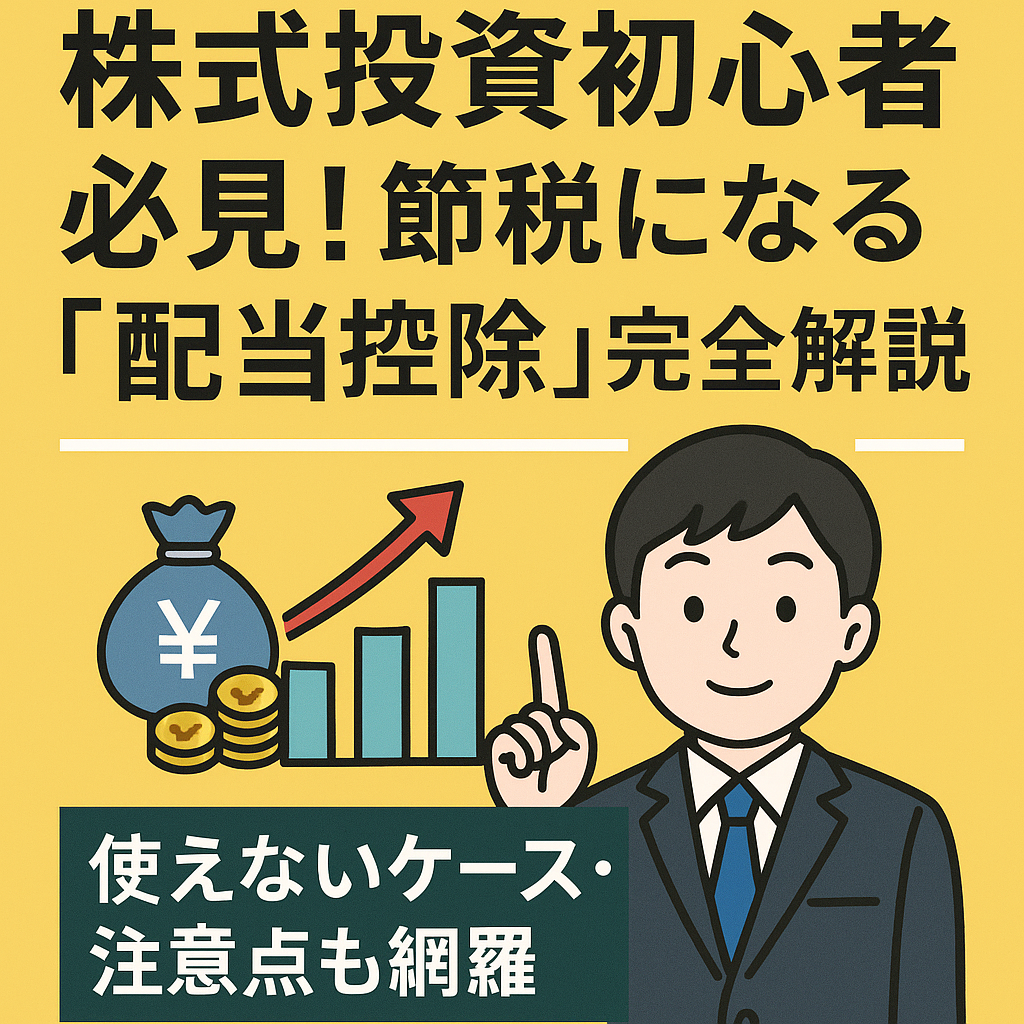


コメント