にほんブログ村
こんにちは、りらくです!

最近は株価がどんどん上がってる!
株価がグングン上がる上昇相場に出会うと、証券口座を開くたびに資産が増え、まるで自分が天才投資家になったような錯覚を覚える瞬間ってありますよね。
でも、歴史を振り返ると、上昇相場で冷静さを失った投資家は、その後の反落で大きな損失を出してしまうことが少なくありません。
今回は、「上昇相場でやってしまいがちな失敗」と「それを避けるための具体的なポイント」を、初心者にもわかりやすく、過去の相場事例を交えて解説します。
目次
上昇相場が生む心理のワナ
株価が右肩上がりに伸びていく上昇相場では、投資家の心理は大きく揺れます。
評価額が増えると、私たちはついこんな風に思ってしまいます。
- 「自分は投資の才能があるかも」(実際は相場環境が良いだけ)
- 「もっと上がるだろう」(利確タイミングを逃す)
- 「資金を追加すればさらに儲かる」(リスクが過剰に膨らむ)
この心理は、特に初心者が「実力と運の区別がつかなくなる」原因になります。
具体例:日経平均が3万円を突破した2021年
コロナ後の金融緩和と世界的な株高を背景に、日経平均は約30年ぶりに3万円台を回復しました。
SNSには「株で資産倍増」の声があふれ、証券口座の開設数も急増。
しかしその後、半導体不足やインフレ懸念から株価は調整に入り、「もっと上がる」と買い増した人が含み損を抱えるケースが目立ちました。
教訓:上昇相場の利益は「市場の追い風」によるもので、自分の実力と錯覚しないこと。

自分の能力を過信しすぎることも良くないね
天井圏のサインを見極める
上昇相場は永遠には続きません。過去の事例を見ると、ピーク付近では市場が過熱しやすく、いくつかの共通サインが現れます。
天井圏でよくあるサイン
- 出来高が急増する:短期間で取引が加熱
- 好材料が出尽くす:好決算やポジティブニュースでも株価が上がらない
- ニュースやSNSで過剰報道:株に興味がなかった層まで参入
- 急騰銘柄に資金集中:テーマ株や小型株が連日のストップ高
具体例:ITバブル(2000年)
米国NASDAQはインターネット関連株が急騰し、「この時代は株価が永遠に上がる」というムードに。
しかし、利益確定売りと業績未達の失望が重なり、株価はわずか数か月で半値以下に下落。
教訓:天井を完璧に当てることはできませんが、「過熱の兆候」を見たら警戒を強めることが重要。

見極めることは難しいけど、「過熱の兆候」は見逃さないようにしよう
過剰なレバレッジは命取り
上昇相場が続くと、短期間で大きな利益を狙いたくなる心理が働きます。そこで手を出しがちなのが信用取引やレバレッジ型ETFです。
しかし、上昇相場に浮かれてレバレッジを使うのは非常に危険です。
なぜ危険か?
- 信用取引では含み損が膨らむと追証(追加保証金)が発生
- レバレッジETFは日々の値動きで長期保有の期待値が低下
- 相場反転時に損失が短期間で急拡大
具体例:コロナショック前の米国株ブーム(2020年初頭)
米国株が好調で、レバレッジETF(TQQQなど)や信用取引で全力投資する個人投資家が急増。
しかし2020年3月、コロナショックで市場が急落し、1か月で資産の半分以上を失ったケースも珍しくありませんでした。
教訓:レバレッジは上昇相場に浮かれて使うものではなく、明確な短期戦略と損切りルールが必須。
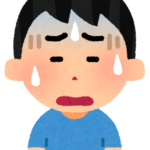
投資は余剰資金で始めて、基本的にレバレッジには手を出さない方が良いね
分散投資と利益確定の重要性
上昇相場では、特定の銘柄やセクターが急騰します。
「集中投資で効率的に稼ごう」と思うかもしれませんが、これは利益が一瞬で吹き飛ぶリスクを抱えています。
なぜ分散が必要か?
- 特定セクターの下落リスクを軽減(例:半導体バブル崩壊)
- 市場全体の調整に備える(複数資産を組み合わせることで変動を緩和)
- 長期投資で安定したリターンを狙える
分散の実践方法
- 業種分散:ハイテク・金融・生活必需品・エネルギーなど
- 地域分散:日本株だけでなく米国株、新興国株にも配分
- 資産分散:株式に加え、債券や現金、REIT(不動産投資信託)も検討
具体例:リーマンショック(2008年)
リーマンショック時、金融株に集中投資していた投資家は株価暴落で甚大な損失を被りました。
一方、資産を分散していた投資家は損失を抑え、下落後の回復相場にも参加する余力を残せました。
教訓:上昇相場こそ分散を意識し、利益を守る姿勢が必要。

やはり損失を抑えるためには分散が重要だね!
上昇相場で利益確定を怠らない
上昇相場の一番の落とし穴は、「もっと上がるはず」と利益確定を先延ばしすることです。
なぜ利確が難しいのか?
- 「売った後にさらに上がったら悔しい」という心理
- 「利益確定=負けた気がする」という誤解
- 上昇中の雰囲気に流されて冷静さを失う
利益確定の実践方法
- 含み益が20〜30%を超えたら一部利益確定
- 定期的なポートフォリオのリバランスで利益確保
- 目標株価や保有期間を事前に設定しておく
具体例:日経平均バブル期(1989年)
バブル期、日経平均は4万円目前まで上昇しました。
「もっと上がる」と誰もが思っていた中、利益確定をしなかった投資家は、その後の暴落で含み益を失い、場合によっては元本割れを経験しました。
教訓:上昇相場の利益は幻になりやすい。計画的な利確は「利益を守る行動」であって「損をする行動」ではない。

投資を始める前に、利益確定のルールを自分の中で定めておくと良いね
上昇相場の終わりと次のチャンスへの備え
上昇相場の後には、ほぼ必ず調整や下落が訪れます。
これは脅しではなく、過去の相場を見れば「上昇→調整→再上昇」の繰り返しが歴史的なパターンです。
なぜ下落はチャンスか?
- 株価が割安水準に戻ることで長期投資の仕込み時になる
- 上昇相場で温存した資金を有効に投入できる
- 感情的に売られた優良銘柄を安値で買える
具体例:コロナショック(2020年3月)
日経平均はわずか1か月で3割以上下落しましたが、その後の金融緩和と経済対策で株価は急回復。
暴落時に冷静に買い向かった投資家は、1年足らずで大幅な利益を得られました。
次のチャンスに備える行動
- 上昇相場で資金をフル投入しない
- 下落時に買いたい銘柄や投資信託のリストを作っておく
- 過去の調整局面の値動きを学び、心の準備を整える
教訓:上昇相場は終わりを意識しながら、次の暴落をチャンスに変える準備をすることが大切。

こう考えると、下落したからと焦ったり恐がる必要はないね!
まとめ|上昇相場はチャンスとリスクが表裏一体
上昇相場は資産を一気に増やす絶好のタイミングですが、その裏側には浮かれすぎや過信による落とし穴が隠れています。
過去の相場を振り返ると、上昇相場で冷静さを保てた人ほど、次の局面で大きなリターンを得られています。
上昇相場で最も大切なのは、利益を増やすこと以上に「利益を守ること」です。
冷静さを保ち、次の相場局面への準備を進めることで、上昇相場を単なる一過性の“ラッキー”で終わらせず、長期的な資産形成へと繋げることができます。

株価で一喜一憂せずに、常に冷静な判断ができるように心掛けましょう!
それでは、今回の内容は以上となります!
今回も読んでいただき、ありがとうございました!!
もしこの記事が良かったら、SNSでの共有および以下をクリックしていただけると大変喜びます!
にほんブログ村

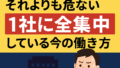

コメント